『キングダム』に登場する魏の知将・呉鳳明。その冷静沈着な戦略と巨大兵器の描写に圧倒されつつ、読者の間では「彼は実在の人物なのか?」という疑問が浮かぶ。本記事では、呉鳳明が史実には存在しない創作キャラであることを踏まえつつ、彼が背負う“魏という国の滅び”を、歴史的事実と重ねて読み解く。水攻めによって滅びた魏、王賁との宿命的な対決、その最期に込められる物語的意味──架空の将が、実在よりも深い「記憶」となる瞬間を追う。
呉鳳明のキャラクター設定
原作における立ち位置・性格・戦略性・創作背景が把握できる
呉鳳明は実在するのか?
中国戦国史における一次資料から、実在性の有無が明確になる
魏という国の滅亡の歴史
紀元前225年の大梁陥落、水攻めによる滅亡の過程がわかる
呉鳳明の“最後”の考察
作中で描かれるであろう死の意味と、物語的な役割を深掘り
架空の人物がもたらす感情のリアル
フィクションが史実を補完するという作品論的意義が見える
朝倉透の独自考察
「実在しないからこそ人の記憶に残る」という逆説的命題に迫る
はじめに──魏という国に、心を預けた男
その姿は、まるで“城”のようだった──。
『キングダム』における魏の将軍・呉鳳明。大軍を率いるにふさわしい風格と、戦術に長けた頭脳。だが、そのまなざしにはいつもどこか、寂しげな影があった。
筆者は長年アニメ評論をしてきたが、呉鳳明のようなキャラクターに出会うと、どうしても“その背負っているもの”を知りたくなってしまう。なぜなら彼は、物語の中で「国の論理」と「人の情」のはざまに立つ、いわば“中間の者”だからだ。
本稿では、「呉鳳明は史実に実在したのか?」という問いからはじめ、その“最後”を史実の魏滅亡と重ねて読み解いていく。
彼が“いないはずの人物”であることが、むしろ私たちに問いかけてくる──そんな逆説を辿る旅の始まりだ。
呉鳳明とは何者か──知略と孤独の系譜
| 時期・場面 | 出来事 | 人物としての特徴 |
|---|---|---|
| 初登場(魏の総大将) | 父・呉慶の後を継ぎ、若くして魏軍を指揮 | 冷静沈着、結果重視型 |
| 合従軍編 | 巨大兵器「井闌車」「床弩」などを駆使し、函谷関を攻める | 技術革新と論理的構築力に秀でる |
| 著雍の戦い | 師・霊凰を囮に使い、自らは撤退 | 非情な判断力、個の成果を優先 |
| 現在〜終盤予想 | 魏滅亡戦で王賁と激突? “魏最後の将”としての最期が描かれると予想される | “理性の将”が“情”を取り戻す可能性 |
『キングダム』において、呉鳳明は魏軍の総大将として登場する。彼は父・呉慶(こちらも原作オリジナル)から軍略を叩き込まれ、若くして大軍を任される存在となる。だがその本質は、単なる軍人ではない。
象徴的なのは、合従軍編での巨大兵器「井闌車(せいらんしゃ)」の投入だ。城壁を越えるための移動式兵器であり、あれほどのものを“現実に動かす”構想力と執行力。これはもはや「工学者」の領域だ。
そして呉鳳明は、情に流されることを嫌う。「戦とは、結果を出すこと」が口癖のように、必要とあらば師すら捨てる。
たとえば著雍の戦いで、自らの師・霊凰を囮として見捨てる場面──。あの決断には、「戦とは非情を受け入れること」という信念が垣間見える。
呉鳳明は実在した?──史実に記されぬ名
まず最初に確認しておきたいのは、「呉鳳明という人物は、史実には存在しない」という点だ。
司馬遷の『史記』、戦国策など中国の正史においても、呉鳳明の名は一切登場しない。
この事実は、原泰久氏が“魏の戦略思想”を象徴させるために、独自に創造したキャラクターであることを示唆している。実際、魏という国は「李克」や「呉起」など、史実に名を残す兵法家を多数輩出しているが、彼らとは異なる“別の系譜”として、呉鳳明が設計されているのだ。
 この点において呉鳳明は、歴史ではなく物語の中にしか存在しない。それゆえに、彼の存在が“魏という国の本質”を浮かび上がらせるフィクショナルな装置として、非常に重要な役割を担っていると言えるだろう。
この点において呉鳳明は、歴史ではなく物語の中にしか存在しない。それゆえに、彼の存在が“魏という国の本質”を浮かび上がらせるフィクショナルな装置として、非常に重要な役割を担っていると言えるだろう。
🧠 呉鳳明──“国家そのもの”を体現した男
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名前 | 呉鳳明(ごほうめい) |
| 所属 | 魏(戦国七雄の一国) |
| 役職 | 総大将・第一将軍 |
| 家系 | 父・呉慶(架空の将軍) |
| 初登場 | 合従軍編(函谷関攻防戦) |
🔧 キャラ造形の特徴
- 巨大兵器「井闌車」や「床弩」を発案・運用する技術指揮官
- 「感情は戦に不要」という合理主義者
- 師・霊凰を囮として見捨てるほどの非情な決断力
⚙️ 物語上の役割
- 信や蒙恬ら“信頼を基盤とした戦”の対極としての存在
- 感情と非情、信と疑念──価値観の衝突を描く対比キャラ
- 戦術的な天才でありながら「孤独な天才」の象徴
🧩 考察
呉鳳明とは「信じることのリスクを避け続けた男」である。
だが物語の終盤、魏の滅びと共に彼が“壊れる”ときこそ、人間としての彼が顕れる瞬間かもしれない。
冷徹な計算の果てに見つけた“誰かを守る決断”──そのとき、初めて彼は歴史を超えて記憶される存在になる。
魏滅亡の史実──“水攻め”で終わった国の最期
では、呉鳳明が“いない”とされる史実において、魏という国はどのように終焉を迎えたのか。
紀元前225年、魏の都・大梁(だいりょう)は、秦軍の将・王賁によって攻め落とされる。その手段は極めて象徴的だった。「水攻め」である。黄河の堤防を決壊させ、街ごと沈めるというものだった。
当時の魏王・魏王假は、抵抗の末に降伏。これにより魏は完全に滅び、戦国七雄の一角が姿を消した。
ここで想像してみてほしい──。
もし、呉鳳明のような“戦術の化身”がこの場にいたら、果たしてどう戦っただろうか?
王賁という“対話不能な戦術家”に、彼は何を語り、何を賭けただろうか。
史実とフィクション、そのはざまに浮かぶ幻影。それが、呉鳳明という男の存在理由なのかもしれない。
呉鳳明の“最後”はどう描かれるか──物語的な死の意味
史実にいない者の“死”は、自由である。だがその自由には、必ず“意味”が求められる。
では、呉鳳明の最期はどのように描かれるのか──。
物語の構造上、魏という国家はやがて滅びる運命にある。その時、秦の軍勢に立ちふさがる“魏の最後の砦”として、呉鳳明が登場することは想像に難くない。しかも、相手は王賁──まさに“技巧vs技巧” “矜持vs矜持”の対決になるはずだ。
筆者は、この対決において呉鳳明がただ敗れるとは思っていない。
彼は「冷徹であろうとした者」が、最後に「人として何を残すか」という物語的役割を担っている。
つまり、彼の死は「魏の美学」と「個人の和解」が同時に起きる場所になる。
それは、もしかすると自らの命を賭して民を逃がす選択かもしれないし、または王賁に「君のような将が魏にいたなら」と言わせるだけの戦いかもしれない。
いずれにせよ、呉鳳明の“最後”は、彼が「人間に戻る場所」になると、私は確信している。
“実在しない者”が歴史と重なるとき──まとめにかえて
『キングダム』において呉鳳明は、史実には存在しない。だが、彼が語る戦略、決断、そして孤独には、実在の誰かが込められているように思える。
戦国時代という混沌の中で、魏という国は“頭脳”によって立ち、“力”によって倒された。呉鳳明はその運命を、誰よりも知っていた者として描かれているのかもしれない。
私たち読者は、彼のような“フィクションの中の真実”を通じて、ただ歴史を知るのではなく、歴史の“痛み”を体験する。
そしてこう思うのだ──「この男が、実在していればよかったのに」と。
物語とは、記録ではない。だが、記憶にはなる。
呉鳳明という男の“最後”が、ただの消滅ではなく「魏という国の魂を語る一瞬」であれば、それはもう、誰よりも実在していたと言えるのではないだろうか。
この記事のまとめ──“いないはずの男”が残したもの
- 呉鳳明は史実に存在しないキャラクターでありながら、魏という国の「終わりの思想」を体現する存在として描かれている
- 知略と非情を武器にする彼の戦いぶりは、他キャラとは一線を画す“合理の象徴”
- 魏滅亡という史実をなぞる形で、物語上の“最後”が重厚に描かれると予測される
- “フィクションの中の真実”として、読者に「実在していないのに忘れられない」印象を残す
- 呉鳳明の死は、国家の終焉とひとりの人間の再生が重なる、物語的クライマックスとなるだろう
歴史に記されない者たちが、私たちの記憶に残る。
それこそが、物語の力であり、アニメや漫画が描ける“もうひとつの歴史”なのだと思う。
呉鳳明という名前が、たとえ教科書に載っていなくとも、
彼の生き様が私たちの中に“在った”ことは、確かだ。
U-NEXTは“キングダム完全戦場
31日間無料トライアル付き。つまり今から登録すれば、1カ月間(トライアル期間)は映画もアニメも漫画も――
実質、無料で攻め放題!!さらに戦いを後押しする特典!
初回登録で600円分ポイントプレゼント!
最新巻の漫画購入や有料映画レンタルに即投入できます。

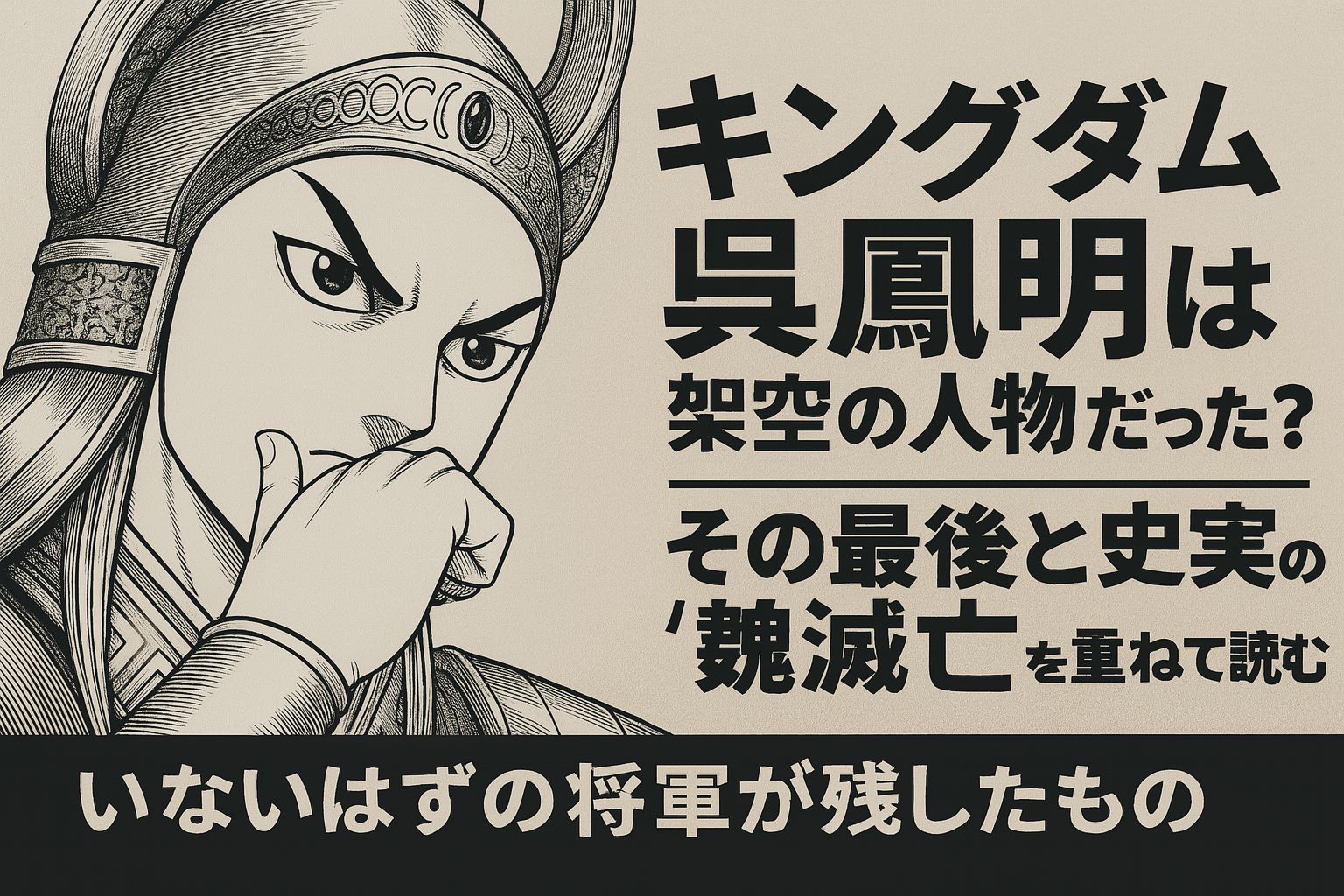
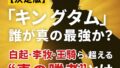

コメント