「王賁(おうほん)は本当に“水攻め”で魏を滅ぼしたのか?」──漫画『キングダム』でも注目されるこの史実は、実在の将軍・王賁が起こした前代未聞の戦術に端を発します。
本記事では、紀元前225年の魏攻略において王賁が行った「水攻め」の詳細を、史実・戦術背景・人物像・最期の観点から徹底的に検証します。
さらに、信・蒙恬とは異なる王賁というキャラクターの“覚悟”と“冷静な戦略”に注目しながら、なぜ彼が中華統一の鍵を握る存在となったのかを、読者とともに掘り下げていきます。
この記事を読むとわかること
王賁という将軍の正体
キングダム内での立ち位置と、史実での実在人物としての姿がわかる
“水攻め”の戦術とその実態
黄河を使った堤防戦術や大梁の地理的条件など、戦略の詳細が理解できる
王賁の人物像と信念の変遷
信や蒙恬との違いから読み解く、冷徹さと覚悟を宿した将軍像が見えてくる
史実における王賁の軍歴と最期
韓・魏・燕・斉の攻略に関わった記録と、その後の消息の謎が整理できる
なぜ“王賁=水攻め”と語られるのか
歴史的に稀な成功例として、王賁の名が残り続ける理由を読み解ける
今後の原作・実写展開で注目される理由
映像化や漫画で描かれる可能性と、王賁の再評価の動きが理解できる
“水攻め”という異常な戦術が意味するもの
──その日、城の周囲に流れる黄河が、異様な濁りを帯びていた。
「水が迫っている」と城壁の上で呟いた兵士の声が、空気を裂く。
そのとき魏の都・大梁では、ひとつの国の終焉と、一人の将軍の“決断”が交差していた。
「キングダム」で史上最大級の戦術──水攻め。
その中心にいたのは、信・蒙恬とともに中華を駆け抜けた若き将軍、王賁(おうほん)。
この記事では、原作の今後の展開においてキーポイントとなる“魏攻略”と、王賁がなぜ「水攻め」という苛烈な手段を選んだのかを、史実とキャラ背景の両面から読み解いていきます。
そこには、ただの軍略を超えた──人としての覚悟と代償があった。
【王賁の史実経緯】中華統一を支えた“静かなる功労者”
王賁(おうほん)とは──“誇りを飲み込み、戦術で人を沈めた男”
 キングダムにおいて、彼は“信”“蒙恬”と並ぶ“三大将軍候補”の一角でありながら、感情よりも理、激情よりも覚悟を選ぶ、最も寡黙な存在だ。
キングダムにおいて、彼は“信”“蒙恬”と並ぶ“三大将軍候補”の一角でありながら、感情よりも理、激情よりも覚悟を選ぶ、最も寡黙な存在だ。
原作初期では、父・王翦の嫡子としてその才覚を当然視され、他者と交わることのない孤高の武将として描かれていた。だが、やがて戦場で流れる命と想いに触れる中で、「選ばれた者」から「選ばざるを得なかった者」へと変化していく。
史実上の王賁もまた、類まれなる戦略家であった。
- 紀元前225年──魏国の都・大梁を黄河の水で水没させ、魏王を降伏に追い込む。
- 前223〜221年──燕・代・斉を連続制圧。秦による中華統一の総仕上げを担う。
- その後、功績を認められ「通武侯」に封じられるが、統一後まもなく史書から姿を消す。
ここにあるのは、「戦って勝った」英雄ではなく、「勝つために何を捨てたか」を問われた男の物語である。
彼の槍は、人を貫いたが、心を交わすことはなかった。
だが、“中華を統べる”という大義のもと、感情の引き金を引かずに決断を下せること──それこそが王賁の信念であり、時代に求められた器だった。
感情の時代に、あえて無感情を選んだ男。
その背中は、たとえ時代が流れても──どこか、私たちを惹きつけてやまない。
王賁は実在した秦の将軍であり、父・王翦と共に秦の中華統一を大きく支えた人物です。
史料(『史記』など)に記された功績は数多く、以下のような重要戦役に名を刻んでいます。
| 年 | 戦役・出来事 | 内容と功績 |
|---|---|---|
| 前230年 | 韓の滅亡 | 父・王翦と共に韓を滅ぼし、秦の南進を加速 |
| 前225年 | 魏の滅亡(水攻め) | 黄河の水を利用して魏都・大梁を水没させ、魏王を降伏させる。王賁最大の功績 |
| 前223年 | 楚攻め | 王翦が主将、王賁が副将として参戦。楚を滅亡へ |
| 前222年 | 燕・代の平定 | 遼東に逃れた燕王を追い詰め、燕国を完全制圧 |
| 前221年 | 斉の降伏 → 中華統一 | 斉を無血開城に追い込み、秦による中華統一が完成 |
| ✅ 王賁に関する補足情報(史実ベース) | |
|---|---|
| 称号 | 「通武侯」に封じられ、軍功を国家から正式に認められた。 |
| 死亡時期 | 明確な記録なし。秦統一(前221年)後まもなく史料から姿を消す。病没または隠棲と推定される。 |
| 戦術的評価 | 魏都・大梁を沈めた「水攻め」は戦術史上でも希少な成功例。王賁の代名詞ともされる。 |
王賁は本当に“水攻め”で魏を滅ぼしたのか?
結論から言えば、王賁こそが魏滅亡の立役者であり、水攻めの実行者でした。
紀元前225年──秦軍は魏の首都・大梁を包囲した。
大梁は黄河と汴水(べんすい)に囲まれた水の要塞都市で、難攻不落と見なされていた。
この難攻の城に対し、王賁が選んだ戦術は──「水攻め」。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 地形利用 | 大梁は黄河と支流に囲まれ、水害に弱い低地にあった。 |
| 戦術内容 | 堤を築いて水を蓄え、一気に放流。洪水によって城を破壊。 |
| 結果 | 市街が水没し、魏軍に壊滅的被害。魏王・假は降伏。 |
| 評価 | 非情ながらも、最小戦力で最大成果を上げた戦術として高評価。 |
🌊 再現:その瞬間、何が起きたのか?
その日は不気味なほどに風がなかった。
堤の奥から崩れる音が響いた瞬間──
黒い壁のような水が、城壁を越えて押し寄せた。
王賁は動かなかった。
その目で、兵も民も、城も決断も、すべてを呑み込む“戦略”を見届けていた。
⚖️ なぜ王賁は「水攻め」を選んだのか?
| 判断要素 | 内容と背景 |
|---|---|
| 短期決着が必要 | 魏を滅ぼすことで秦の東進ルート(斉・燕)を早期に確保したかった。 長期戦になれば他国の介入リスクも増すため、戦略的に早期制圧が求められた。 |
| 被害と犠牲は承知の上 | 民間人を巻き込む可能性も高い水攻めは、非情な選択。 だが総戦費・人的損耗を抑える合理的な“損切り”戦術でもあった。 |
| 王賁自身の特性 | 王翦譲りの知略と冷静な判断力を受け継ぎ、信のような熱血型ではなく、現実を読む戦略家として非情な選択もできる性格が如実に表れた。 |
王賁の「水攻め」は単なる奇策ではない。
地形・時間・心理・犠牲──すべてを読み切った上で下した、決して引き返せない決断だった。
魏王・假(け)にとっては、戦で負けたのではない──国そのものが“沈んだ”のです。
この作戦には多くの犠牲がつきまといました。城内の兵士だけでなく、民衆までもが水に呑まれたとも記されており、それは“勝利”という言葉だけでは片づけられない、重さを王賁に刻みつけたはずです。
信のように「正義」を信じ、蒙恬のように「人心」を読むことに長けた者ならば、この決断を回避したかもしれない。
それでも、王賁は進んだ──中華統一のために。
王賁という将の変遷──“誇り”から“覚悟”へ
「あの男は、戦うために生まれてきたようなものだ」──作中の仲間たちが口にする王賁の印象は、常に冷静で、どこか孤高だ。
初登場時の王賁は、王翦の嫡男という血統に誇りを抱き、誰よりもストイックに「大将軍」への道を見据えていた。玉鳳隊を率い、その才と技はまぎれもなく本物だった。
だが、彼には致命的な“欠落”があった。それは──他者との共鳴。
信と蒙恬との出会い、それぞれが持つ“背負うもの”や“人間臭さ”に触れるたびに、王賁の内面に微かな変化が芽生えていく。
槍術では誰にも負けずとも、人を導く器としての“深さ”は、すぐには得られない。
父・王翦の冷徹な知略、母をめぐる家庭環境、自身の出生をめぐる葛藤──そうした積年の影を、王賁はずっと背負っていた。
 そして彼は“誇り”を“覚悟”へと変えた。
そして彼は“誇り”を“覚悟”へと変えた。
それが、魏への水攻めという選択に象徴される。
多くの命が失われると知りながら、それでも進む──その先にしか、父を超える道も、国を救う未来もないと知っていたからだ。
「王賁らしい」とは何か。それは栄光の中に苦悩を沈め、それでも立ち続ける静かな炎──そんな姿に他ならない。
“最後の戦い”ではない王賁の死──史実のその後
魏を沈めたあの“水攻め”──それが、王賁の人生の終着点だったわけではない。
紀元前225年、大梁を水没させたのちも、彼の戦いは続いていた。
- 紀元前222年──燕の遼東へ逃れた王喜を追撃し、燕を完全制圧。
- 紀元前221年──斉を攻め、そのまま秦の中華統一を完成させる。
だが、その後──王賁は史書から忽然と姿を消す。
『史記』や『戦国策』などに彼の死因やその後の政治的動向の記録はほとんど残されていない。
一説には、中華統一直後に病没したとも、あるいは政変を避けて静かに身を引いたとも言われている。それは、まるで「任を終えた者が、自ら歴史の舞台から降りたかのよう」にも見える。
これは、父・王翦も似たような経緯をたどっている。大業の成就とともに歴史の舞台から退場し、英雄でありながら、静かに消えていく。
 “戦場で死ぬ”のではなく、“戦場を超えて終わる”──それが、王家の生き方だったのかもしれない。
“戦場で死ぬ”のではなく、“戦場を超えて終わる”──それが、王家の生き方だったのかもしれない。
王賁にとっての“死”は、戦場ではなく、大義を果たしたその先にあったのかもしれない。
それは、己の命よりも国家と民を背負った将軍にのみ許される、“静かな死”だった。
実写化の可能性──なぜ王賁が今、注目されているのか
今、「王賁」という名前が再び熱を帯びている。
それは、ただ“人気キャラ”だからではない。原作で間もなく描かれるであろう魏攻略編──そこに隠された戦術的衝撃と、歴史の重みが、読者の関心を一気に集めているのだ。
なかでも注目されるのが、やはり“水攻め”という異色の戦術。
戦術で都市を沈める──それは視覚的にもインパクトが強く、映像作品での演出映えが想像しやすい。
すでに4作目まで公開された映画『キングダム』シリーズにおいて、信・蒙恬と並ぶ“三英傑”のひとりである王賁が、次回作以降で本格的に登場する可能性は極めて高い。
そして、彼が主導する魏攻略──特に“大梁水没”のシーンが実写化されれば、それはシリーズ屈指のハイライトになるだろう。
 「王賁って誰?」「どうやって魏を滅ぼしたの?」「あの水攻めって実話?」
「王賁って誰?」「どうやって魏を滅ぼしたの?」「あの水攻めって実話?」
──そんな問いが、次々とネットを飛び交う時代が、もうそこまで来ている。
王賁という男は、静かに燃えている。
そしてその火は、これから確実に“メジャーな炎”になる。
【まとめ】水に沈んだのは城か、それとも王賁の覚悟か──静かなる将の終わり
歴史に名を残す将軍は数多くいる。だが、その中で「国を沈めた者」はどれほどいるだろうか。
王賁が選んだ戦術──水攻め。それは合理と非情、使命と犠牲の狭間で選ばれた決断だった。
誰もが引き返したくなる場面で、彼は“進む”という選択をした。
それが、父を超える道であり、自分の誇りを守る戦いだった。
そして、その先に待っていたのは、栄光でも名声でもなく、静かな終焉。
王賁がどのように死んだか──それを私たちは知らない。
だが、それでいい。
彼の生き様は、「どこで死んだか」ではなく、「何を背負って、何を選んだか」にこそ、物語がある。
それが、「キングダム」という物語が描く“大将軍たちの肖像”の真髄なのだ。
この記事のまとめ
- 王賁は実在した秦の将軍であり、韓・魏・燕・斉の攻略に関わり、中華統一を支えた
- 中でも魏国攻略時の「水攻め」は、戦術史上でも類を見ない大胆な作戦であった
- 水攻めによる勝利は、戦闘ではなく地形と決断による心理戦の結晶でもある
- 原作『キングダム』では、信・蒙恬と異なる王賁の「覚悟」の描写が物語の深みを支えている
- 史実では統一後に消息を絶ち、戦死ではなく静かな幕引きを迎えたとされている
- 王賁という存在は、「何を背負い、何を選んだか」で評価されるべき将である
U-NEXTは“キングダム完全戦場
31日間無料トライアル付き。つまり今から登録すれば、1カ月間(トライアル期間)は映画もアニメも漫画も――
実質、無料で攻め放題!!さらに戦いを後押しする特典!
初回登録で600円分ポイントプレゼント!
最新巻の漫画購入や有料映画レンタルに即投入できます。


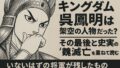
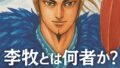
コメント